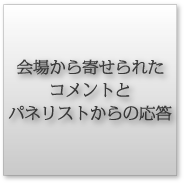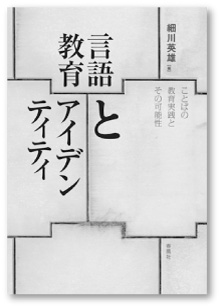国際研究集会「言語教育とアイデンティティ形成─ことばの学びの連携と再編」
プログラム
第1日:2011年3月5日(土)
- 14:00~14:20
- 開会挨拶,趣旨説明「国際研究集会『言語教育とアイデンティティ形成―ことばの学びの連携と再編』に向けて」
- 細川英雄 (早稲田大学)
- 14:20~15:30
- 基調講演(フランス語:通訳つき)
- アリーヌ・ゴアール=ラデンコヴィック (Aline Gohard-Radenkovic,フランス語教育:スイス・フリブール大学),
通訳:山本冴里 (早稲田大学) - 15:45~16:45
- パネルシンポジウム「言語教育とアイデンティティ形成―ことばの学びの連携と再編」
- 森美智代 (国語教育:鈴峯女子短期大学),川上郁雄 (年少者日本語教育:早稲田大学),細川英雄(言語文化教育:早稲田大学),アリーヌ・ゴアール=ラデンコヴィック,
司会:牲川波都季 (言語表現教育:秋田大学) - 16:45~17:30
- 全体討論
- パネリスト,会場にお越しの皆様
第2日:2011年3月6日(日)
| 201会場 | 202会場 | |
|---|---|---|
| 10:00~ | 個人発表 A | - |
| 11:30~ | 昼休み | ポスター発表 |
| 13:30~ | 個人発表 B | |
| 15:00~ | 休憩 | |
| 15:30~ | 個人発表 C | - |
| 17:00~ | 閉会 | |
個人発表 A (10:00~11:30,201会場)
| 10:00 | 〈国語〉と〈華語〉のあいだ ― 再編される台湾の小中学校言語教育課程 | 林初梅 (台湾師範大学台湾文化及言語文学研究所) |
|---|---|---|
| 10:20 | 日本において母語・継承語・継承文化教育をどう位置づけるか | 福田浩子 (茨城大学人文学部) |
| 10:40 | 日本語教育実践において自己を見つめることの意味 ― 「自分史を書く」クラスの実践から | 尾関史 (早稲田大学日本語教育研究センター) |
| 11:00 | 質疑・全体討論 | ディスカッサント |
個人発表 B (13:30~15:00,201会場)
| 13:30 | 言語とアイデンティティは切り離せるか ― フランス植民地言語教育政策における言語同化主義の理念と実践 | 西山教行 (京都大学) |
|---|---|---|
| 13:50 | 言語で生きる ― 「母語」「母国語」「外国語」をめぐる葛藤やアイデンティティの揺れを乗り越えて | 鄭京姫 (早稲田大学日本語教育研究センター) |
| 14:10 | 「場」としての日本語教室の意味 ― 韓国人留学生のライフストーリーから | 三代純平 (徳山大学経済学部) |
| 14:30 | 質疑・全体討論 | ディスカッサント |
個人発表 C (15:30~17:00,201会場)
| 15:30 | 「書く」ことと「民主主義」の構想 ― 戦後の生活綴方の実践をめぐって | 鈴木園巳 (一橋大学大学院言語社会研究科) |
|---|---|---|
| 15:50 | 学習者のアイデンティティを形成・更新することばの学び ― 日本語クラスにおける他者との理解・受容・統合の過程を通して | 寅丸真澄 (早稲田大学大学院日本語教育研究科) |
| 16:10 | 支援者が子どもに付与する「アイデンティティ」と日本語教育実践の関係 ― ある中学生に対する支援者4名の実践報告メールから | 太田裕子 (早稲田大学留学センター), 田邉裕理 (早稲田大学系属早稲田渋谷シンガポール校) |
| 16:30 | 質疑・全体討論 | ディスカッサント |
ポスター発表 (11:30~15:30,202会場)
| ブース A | ||
|---|---|---|
| ある外国人児童の2つのことばとアイデンティティ | 滑川恵理子 (お茶の水女子大学大学院) | |
| 教育言説としての「学習者ニーズ」 | 牛窪隆太 (早稲田大学大学院日本語教育研究科) | |
| 「異なった日本語教育」としての主体性はどのように形成されたか ― 「京都にほんごリングス」に加盟した教室運営者を対象とした聞き取り調査から | 許之威 (京都大学大学院人間・環境学研究科) | |
| ディスカッサント | ||
| ブース B | ||
|---|---|---|
| 「私が私である」ための表現授業 ― 「教室」を「現場」と捉えた授業デザイン | 江原美恵子 (早稲田大学日本語教育研究センター) | |
| 学習者が社会的歴史的に自分を位置づけることとは ― 自分にとってのことばの意味に向き合う | 山口友里恵 (早稲田大学大学院日本語教育研究科) | |
| ディスカッサント | ||
| ブース C | ||
|---|---|---|
| 言語教育実践者による「自己発見」のプロセス | 山本晋也,秋田美帆,山口友里恵,伊藤剛志 (いずれも早稲田大学大学院日本語教育研究科) | |
| 桜の花びらとことば ― 自己表出としてのことば | 深江新太郎 (九州大学大学院統合新領域学府) | |
| リビジョニストの視点よりアイデンティティ形成へのカリキュラムを考える ― 国語教科書低学年用とアメリカで使用されている日本語教科書の比較研究から | 大須賀茂 (シートン・ホール大学) | |
| 日本の小・中・高で学んだ「外国につながる大学生」と言語教育・学習・アイデンティティ ― 大学の国際化をめぐって | 武一美 (多文化共生教育ネットワークかながわ・早稲田大学日本語教育センター), 井草まさ子 (多文化共生教育ネットワークかながわ・たぶんかフリ―スクールよこはま) | |
| ディスカッサント | ||